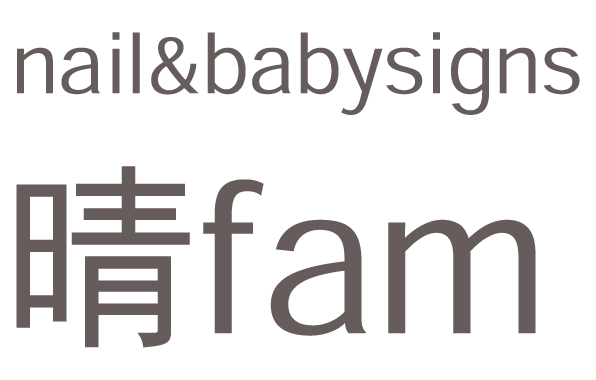はじめてのママ必見!赤ちゃんと話せる⭐️ベビーサインの効果と始め方
ベビーサインとは?基礎知識とその魅力
ベビーサインの定義と歴史
ベビーサインとは、赤ちゃんと簡単な手話やジェスチャーを使ってコミュニケーションを取る育児法です。まだ言葉を話せない赤ちゃんでも、日常生活でよく使う動作やシンプルな表現を通じて気持ちや欲求を伝えることができます。このユニークなコミュニケーション方法は、1990年代にアメリカで始まりました。その背景には、1980年代にカリフォルニア大学で行われた研究があります。この研究を元に、ベビーサインは発展し、2000年代に入ると日本にも広がりました。現在では、ベビーサイン教室を中心に、多くのママやパパが取り入れている育児方法です。

どのように赤ちゃんと話せるのか
赤ちゃんは言葉での会話ができる前でも、手の動きや表情を使うことで感情や欲求を表現できます。ベビーサインは、この赤ちゃんの自然な動作をサポートし、簡単なジェスチャーを活用してコミュニケーションを図ります。例えば、「飲み物が欲しい」といった気持ちを、小さな手を使って特定の動きで表現することが可能です。この方法によって、乳幼児でもスムーズに親とコミュニケーションを取ることができ、育児ストレスの軽減にも繋がります。
ジェスチャーと手話の違い
ベビーサインは手話に似ている部分もありますが、厳密には異なります。手話は聴覚障害を持つ人々のための言語体系ですが、ベビーサインは赤ちゃん向けにアレンジされた簡単なジェスチャーが基本です。手話では正確な文法や構造が求められるのに対し、ベビーサインでは赤ちゃんが理解しやすく楽しい動きを重視しています。そのため、ジェスチャーは遊び感覚で取り入れやすく、ママやパパも気軽に活用できるポイントが魅力です。
手話を赤ちゃんでも使いやすように応用したものもあります。動きが決まったサインもありますが、赤ちゃんが使いやすいように、また、ママパパやご家族が覚えやすようにアレンジしても構いません。
ベビーサイン育児を独学でしていくと、サインの種類や使い方、覚えられないなどでぶつかる壁もあります。私も実際にありました。アレンジのアイディアが浮かばない、これを伝えたいけどサインがわからない(作れない)など困った際はご相談ください◎
どんな赤ちゃんでも使える?
ベビーサインは、特定の赤ちゃんだけでなく、基本的にはすべての乳幼児が使える方法です。特に、生後6ヶ月頃のお座りができる頃から少しずつサインを理解し使い始めます。ただし、赤ちゃんによって習得スピードに個人差があるため、焦らず気長に実践することが大切です。また、日常生活に自然に取り入れることで、赤ちゃんが新しいサインを学ぶ過程がよりスムーズになります。このようにどんな赤ちゃんにも優しい方法だからこそ、多くの育児家庭で広く採用されています。
6ヶ月になる前からママパパが日頃からベビーサインをしていると、赤ちゃんがサインを使い始める前からより多くのサインの種類を用意しておくことができます!
ママパパも覚える時間ができ、赤ちゃんがサインを使い始めた時に「これはどう伝えよう?」と悩まず、コミュニケーションを取りやす苦なりますよ♪
ベビーサインの効果:親子の絆を深める理由
赤ちゃんの感情表現力を引き出す
ベビーサインは、まだ言葉を話せない赤ちゃんが自分の気持ちや欲求を表現するための簡単なツールです。手話やジェスチャーを活用することで、「お腹が空いた」や「眠い」といった自分の状態を伝えることができます。これにより赤ちゃんの感情表現力が自然と育まれ、親が赤ちゃんの思いを理解しやすくなります。

親子のストレスを軽減する効果
赤ちゃんが泣いている理由がわからないと、育児においてストレスを感じることがあります。しかしベビーサインを使えば、赤ちゃんが簡単なジェスチャーで意思を伝えることができるため、お互いのコミュニケーションが成立しやすくなります。この方法は育児ストレスを大幅に軽減し、親子で穏やかな時間を過ごす助けになります。
早期コミュニケーション発達のサポート
ベビーサインは赤ちゃんが言葉を覚える前からコミュニケーションを取るスキルを育てるため、言葉の発達を促進する効果があります。「伝える」「理解する」という基本的なコミュニケーションの仕組みを早期に学ぶことで、その後の言語発達にも良い影響が見られるとされています。
自己肯定感を育む仕組み
自分の欲求が理解され、「伝わった」という感覚を得ることは、赤ちゃんにとって重要な経験です。それは「自分の声に価値がある」と感じるきっかけとなり、自己肯定感を高める助けとなります。また、親が赤ちゃんのサインに積極的に反応することで、赤ちゃんは「認められている」という安心感を得やすくなります。

赤ちゃんに「自分の意見を言ってもいいんだよ」「気持ちや考えを伝えていいんだよ」と教えることにもベビーサインはとっても効果的です!
意見や考え、気持ちを「伝わるように伝える」ことは、これからの時代は特に大切なことだと思います。
イヤイヤ期にも効果的な理由
ベビーサインは、イヤイヤ期にも役立つと言われています。この時期の赤ちゃんは自分の気持ちを表現する言葉が不足しているためにストレスを感じることがありますが、サインを使えることでそのフラストレーションを和らげることができます。また、サインを通じたコミュニケーションが「楽しい」と感じることで、親子の対立が減り、育児がスムーズに進むケースも多いです。
ベビーサインの始め方と実践方法
ベビーサインを始める時期と準備
ベビーサインを始める時期は、生後6ヶ月頃が目安とされています。この時期の赤ちゃんは手指を動かすことができ、言葉を話せる前でも周囲とのコミュニケーションに興味を持ち始めるため適しています。また、赤ちゃんがサインを使って応えるのは、お座りが安定する8~9ヶ月頃が一般的です。
準備として、6ヶ月になる前にママやパパはまず基本的なサインを覚えることからスタートしましょう。最初は、本やベビーサイン教室を利用して基礎を学ぶのがおすすめです。サインを日常生活にスムーズに取り入れるためにも、リラックスした状態で赤ちゃんと向き合うことが大切です。
教室では本だけではわからないことも知ることができ、ベビーサインや育児について相談することもできたり、その後のサポートも受けられます◎
覚えやすい基本的なサインの種類
ベビーサインを始める際には、赤ちゃんが興味を持ちやすい基本的なサインから始めると良いです。例えば、お腹が空いたことを伝える「おっぱい」や「ごはん」、眠いときに使う「ねんね」など、日常で使う場面が多いものがおすすめです。また、「ありがとう」や「バイバイ」などの簡単なジェスチャーも赤ちゃんに覚えやすいです。これらは手話を簡略化した動きが多く、赤ちゃんが自然に真似しやすくなっています。最初はよく使う2~3個のサインから始め、慣れてきたら少しずつ増やしていくと良いでしょう。
日常生活に取り入れるコツ
ベビーサインを日常生活に取り入れるためのポイントは、赤ちゃんが楽しみながら覚えられる環境を作ることです。例えば、「おっぱい/ミルク」のサインであれば、授乳をするタイミングで毎回使い、言葉とジェスチャーを一緒に繰り返します。
また、赤ちゃんが興味を示したものについて簡単なサインを付け加えるだけで、自然とサインに触れる機会を増やすことができます。さらに、兄弟や家族と一緒に使うことで、赤ちゃんがサインを見る機会が増え、コミュニケーションが楽しいものだと感じられるようになります。
赤ちゃんにサインを教えるポイント
赤ちゃんにサインを教える際には、根気よく繰り返すことが最も重要です。一度教えただけでは習得できないため、毎回同じタイミングでサインを見せることが必要です。また、笑顔で楽しい雰囲気を作り、赤ちゃんがストレスを感じないようにしましょう。ジェスチャーに声を添えることで赤ちゃんが理解しやすくなり、言葉の発達もサポートできます。
さらに、赤ちゃんがサインを真似したり、コミュニケーションをとろうとした場合には、反応してたくさんほめてあげることが大切です。こうすることで、赤ちゃんが自信を持ち、継続してサインを使おうとする意欲が高まります。

よくある質問とその対応法
ベビーサインについて、多くのママが抱える疑問の一つに「すぐに赤ちゃんがサインを覚えてくれない」ということがあります。これは自然なことであり、赤ちゃんには個人差がありますので焦らず続けることが大切です。
また、「生活が忙しくてサインを教える(覚える)余裕がない」という場合には、無理なくできる範囲で取り入れましょう。例えば、1日数回だけ特定の場面で使ったり、楽しみながら行うことで、負担を軽減できます。さらに「どのサインから始めるべきかわからない」という方は、基本的なサインに絞ったり、日本ベビーサイン協会の教室やオンラインリソースを活用するのも良い方法です。
晴famではリアルでのレッスンのほか、オンラインレッスンも対応しています。私が実際に困った経験も元にサポートもしています。まずはお気軽にご相談ください♪
ベビーサインを楽しむための注意点と工夫
サインは伝えるための補助
ベビーサインは赤ちゃんとのコミュニケーションの手助けとなる便利で素晴らしい方法ですが、言葉を添えずに使うと赤ちゃんが言葉を覚える機会を奪ってしまう可能性があります。ジェスチャーや手話だけで伝えようとするのではなく、赤ちゃんに話しかけたり、音や言葉で説明しながらサインを使っていきましょう。こうすることで、赤ちゃんは豊かな言語環境の中で成長できます。
きょうだいや家族と一緒に楽しむ方法
ベビーサインは家族みんなで楽しむことができるコミュニケーション方法です。ママやパパだけでなく、お兄ちゃんやお姉ちゃん、さらには祖父母も含めて参加すると、赤ちゃんとのやりとりがより楽しくなります。家族で共通のサインを覚えることで、きょうだいも「育児」に貢献している感覚を得られるでしょう。赤ちゃんが特定のサインを覚えるタイミングが遅くても、周囲の家族が一緒に使うことで、自然と馴染んでいくことがあります。
サインを覚えない場合の対策
赤ちゃんによってはサインをすぐに覚えないケースもありますが、焦る必要はありません。ベビーサインは赤ちゃんが「言いたい」と思ったときに自然と表現するものです。そのため、無理に教え込もう、使わせようとせず、日常生活の中で楽しみながら自然に使い続けることが大切です。
また、赤ちゃんが興味を持っているものや好きなタイミングに合わせてサインを取り入れると覚えやすくなります。赤ちゃんのペースを尊重しながら、信じて待ってみましょう。
ベビーサイン教室の活用
ベビーサインの始め方に迷ったり、継続が難しいと感じた場合は、ベビーサイン教室を活用してみてください。日本ベビーサイン協会の教室では、先生が効果的な教え方や実践法を指導してくれます。また、教室に参加することで同じ目的を持ったママパパたちと交流でき、育児仲間を作ることもできます。一人で抱え込まず、サポートをぜひ活用してくださいね。

成長後のサインの自然な卒業について
赤ちゃんが言葉を覚え始めると、次第にサインの使用頻度が減ることがあります。これは自然な成長の一環であり、無理に続ける必要はありません。赤ちゃんが話す言葉の代わりにサインを使わなくなったとしても、これまでのベビーサインでのやりとりが親子の絆を深め、赤ちゃんのコミュニケーション能力を育む基盤となっています。サインを卒業するタイミングは個人差がありますが、成長を喜びながら次のステップに進む時期と捉えると良いでしょう。
【この記事を書いた人】
山田さや(6歳男の子、0歳女の子のママ)
初めての子育てで「どうして泣いているの?」と悩んでいた時に出会ったのがベビーサインでした。
言葉が話せない時期でも気持ちを伝えてくれることで、私自身がすごくラクになり、
「もっと多くのママに知ってほしい」と思い活動をしています。
現在は山形県で、ママと赤ちゃんのためのネイルケア専門サロンとベビーサイン教室を運営中。
ベビーサインアドバイザー/子どもの爪(爪切りや爪噛み・指しゃぶり)の専門家としても活動しています。
📩 ご相談、お問い合わせは【公式LINE】へお気軽にメッセージください♪